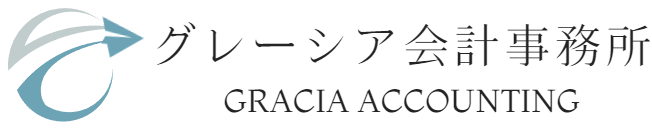法人で社長の持ち家を事務所利用して経費算入する場合の留意点
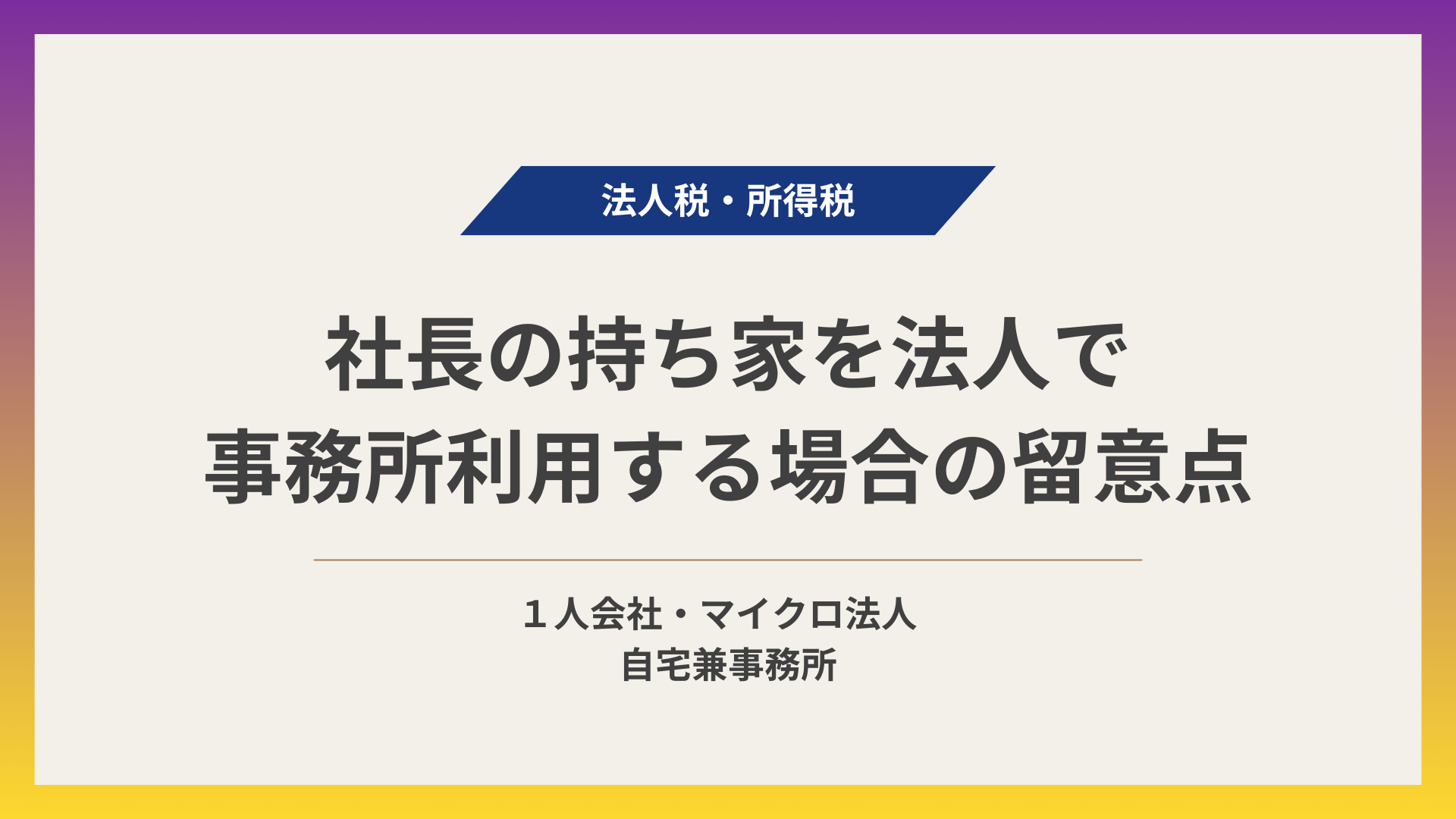
※【免責事項】当記事は投稿日時点に施行される法令に基づき一般的な取扱いを記載したものです。閲覧者が当記事を参考にして行った税務申告は閲覧者自身の責任によって行われ、当記事の内容に誤りがあり閲覧者に損害が生じた場合でも当事務所は責任を負いません。
小規模な法人で、「社長の自宅(持ち家)の一部を社長の会社で利用したい場合の経費処理はどうすれば良いですか?」というご相談をいただくことがあります。
今回は社長が持ち家の場合に、その自宅を法人でも利用する場合の留意点について解説します。
なお、一番ご相談が多いのは社長が賃貸住宅に住んでおりその住宅を法人の事務所としても利用したい場合のご相談です。賃貸借の場合は下記の記事を参考にしてください。
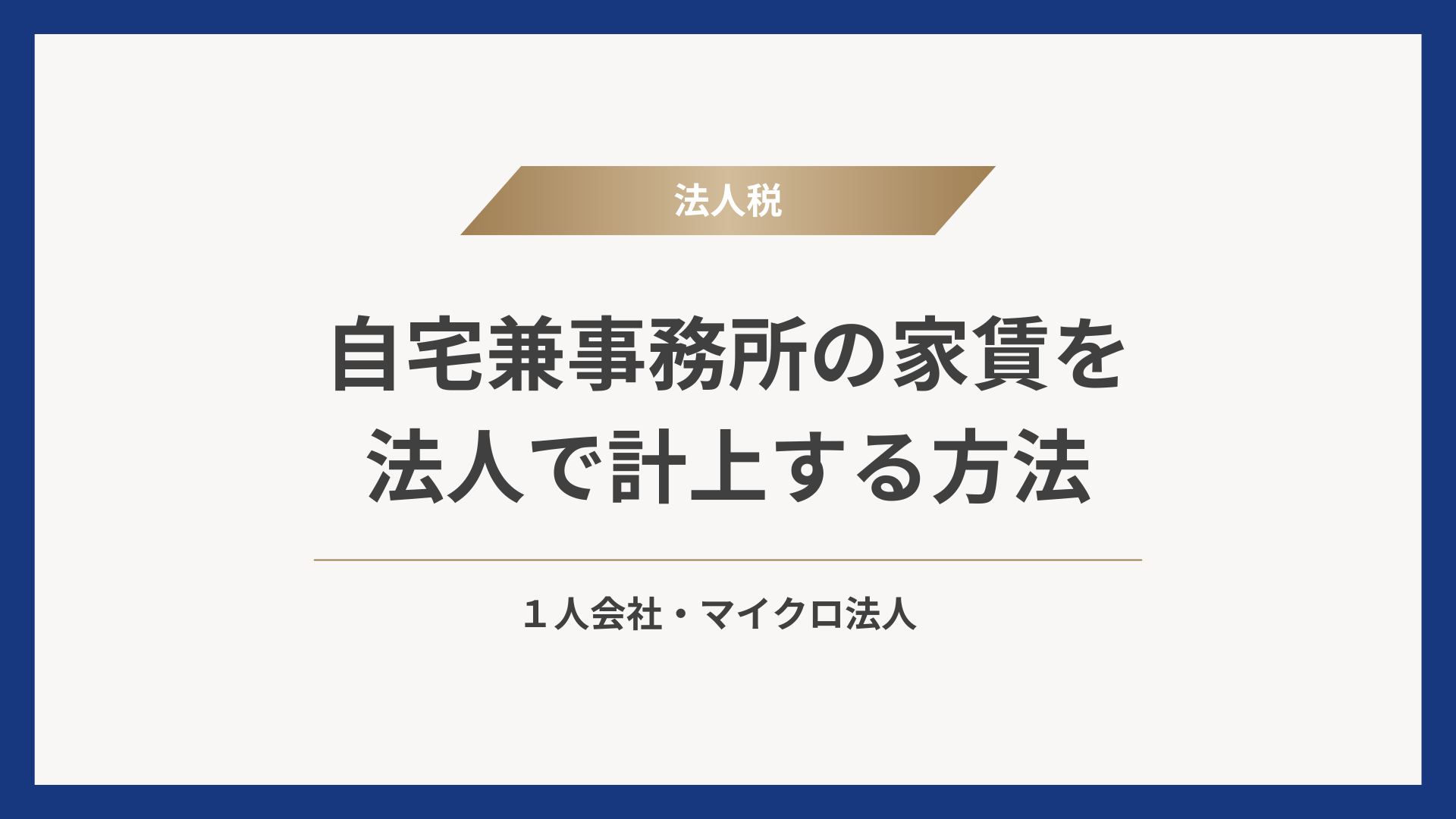
社長の持ち家は法人の損金(経費)にすることが可能
まず、法人が社長個人所有の持ち家の一部を間借りして事業活動を行う場合、法人と社長の間で賃貸借を行うことにより、家賃を法人の損金(経費)とすることが出来ます。賃貸借を行う際、社長自身が株主となる会社だと要らないようにも思えますが、取引に関する証拠書類として賃貸借契約書は必ず作成するようにしましょう。
次に、家賃の決め方です。家賃は時価(第三者価格)となるように設定する必要があります。例えば同等の条件(地価、構造、築年数、面積など)で近隣の家賃相場がいくらなのかを調べて類似する事例があればそれに沿った価格とすることや、建築にかかった費用や維持管理費用など原価面に着目して算出する方法が考えられます。
仮に時価と比べて低額で賃貸借した場合や、高額で賃貸借してしまった場合には、実質的に影響が無いケースと問題が生じるケースがあります。詳しい内容は割愛します。
最後に関連して発生する費用の取扱いです。電気代や固定資産税は法人の事務所利用部分でも発生しますし、場合によっては水道やガスも法人で利用することもあろうかと思います。電気やガス、水道のメーターは通常は1つしか無いため面積基準など合理的な基準で按分し、法人での利用部分については精算するのが適切です。
自宅をオフィス化する場合の留意点
住宅ローン控除との関係性
これまで社長の持ち家の住宅ローン控除を受けていた場合、法人に転貸する部分の面積によっては、住宅ローン控除が受けられなくなる(もしくは減額)になります。具体的には下表のように利用割合によって控除できる率が減少します。
| 住宅利用部分の割合 | 住宅ローンの控除率 |
|---|---|
| 90%以上 | 100%控除可能 |
| 50%以上 | 住宅利用割合と同じ割合だけ控除可能 |
| 50%未満 | 100%控除不能 |
不動産収入が発生するため社長個人の所得税確定申告が必要
法人側の処理だけでなく、社長個人の所得税の計算についても注意が必要です。
社長が法人から受け取った家賃は不動産収入となります。それに対応して、法人に転貸した部分に対応する建物の減価償却や、固定資産税は不動産所得の計算において経費として取り扱われます。不動産収入から必要経費を控除した残額から必要に応じて青色申告特別控除を控除した残額が課税対象となります。
なお、社長個人が自身がオーナーとなる会社から受け取る家賃については必ず確定申告が必要となるため年末調整だけで済ますことが出来ないという点にも注意が必要です。
将来的な売却時も税制上不利になる可能性
現在のことだけでなく将来的なことも留意が必要です。例えば自宅の一部を賃貸していると、自宅を売却する際に居住用不動産の3,000万円控除の特例が使用出来なくなったり、相続後の空き家譲渡の特例が適用出来なくなる可能性があります。
ここまで上げた内容以外にも、自宅兼事務所については課税関係が複雑となり、様々な論点が生じ得えます。自宅兼事務所を設置する前に、しっかりとメリット・デメリットを検討することが望まれます。