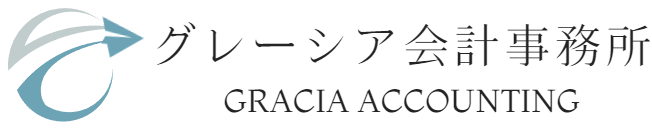法人で社長の自宅兼事務所の賃借料を経費算入する場合の留意点
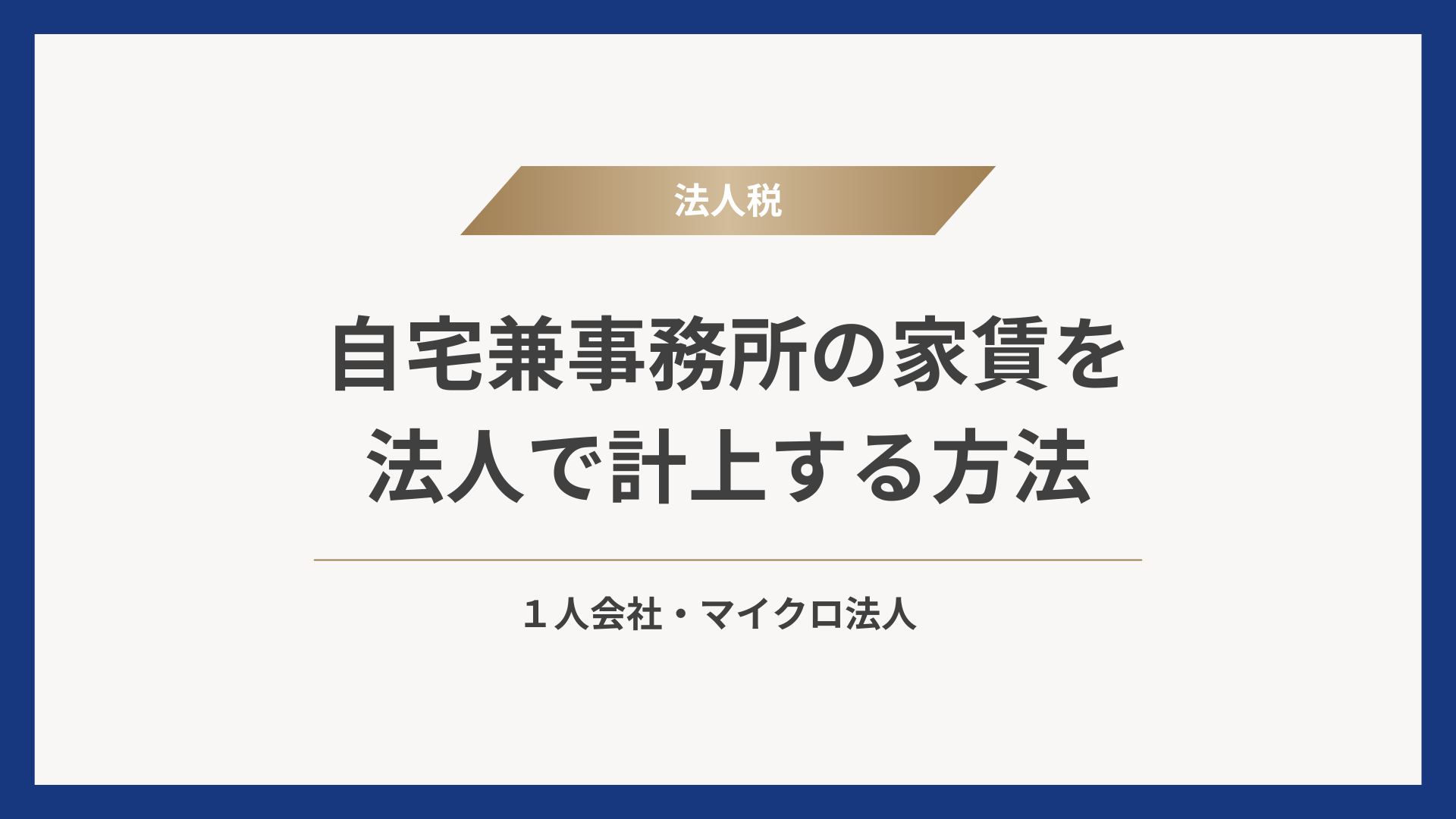
※【免責事項】当記事は投稿日時点に施行される法令に基づき一般的な取扱いを記載したものです。閲覧者が当記事を参考にして行った税務申告は閲覧者自身の責任によって行われ、当記事の内容に誤りがあり閲覧者に損害が生じた場合でも当事務所は責任を負いません。
小規模な法人で、「社長の自宅と法人の本社オフィスを兼用している場合に家賃を法人の経費として計上するにはどうすれば良いですか?」というご相談をいただくことがよくあります。スタートアップ企業や社長1人の会社では外部にオフィスまで借りる必要はなく自宅の一室を利用すれば十分というケースが多く、多くの経営者の方はこの問題で頭を悩ませていると思います。
今回は居住用マンションや借家などを社長の自宅と法人の事業所両方の目的で利用する場合の法人での費用計上の方法について、個人的なメモを兼ねて解説します。
賃貸ではなく社長自己所有の自宅をオフィス利用する場合は下記の記事をご参考ください。
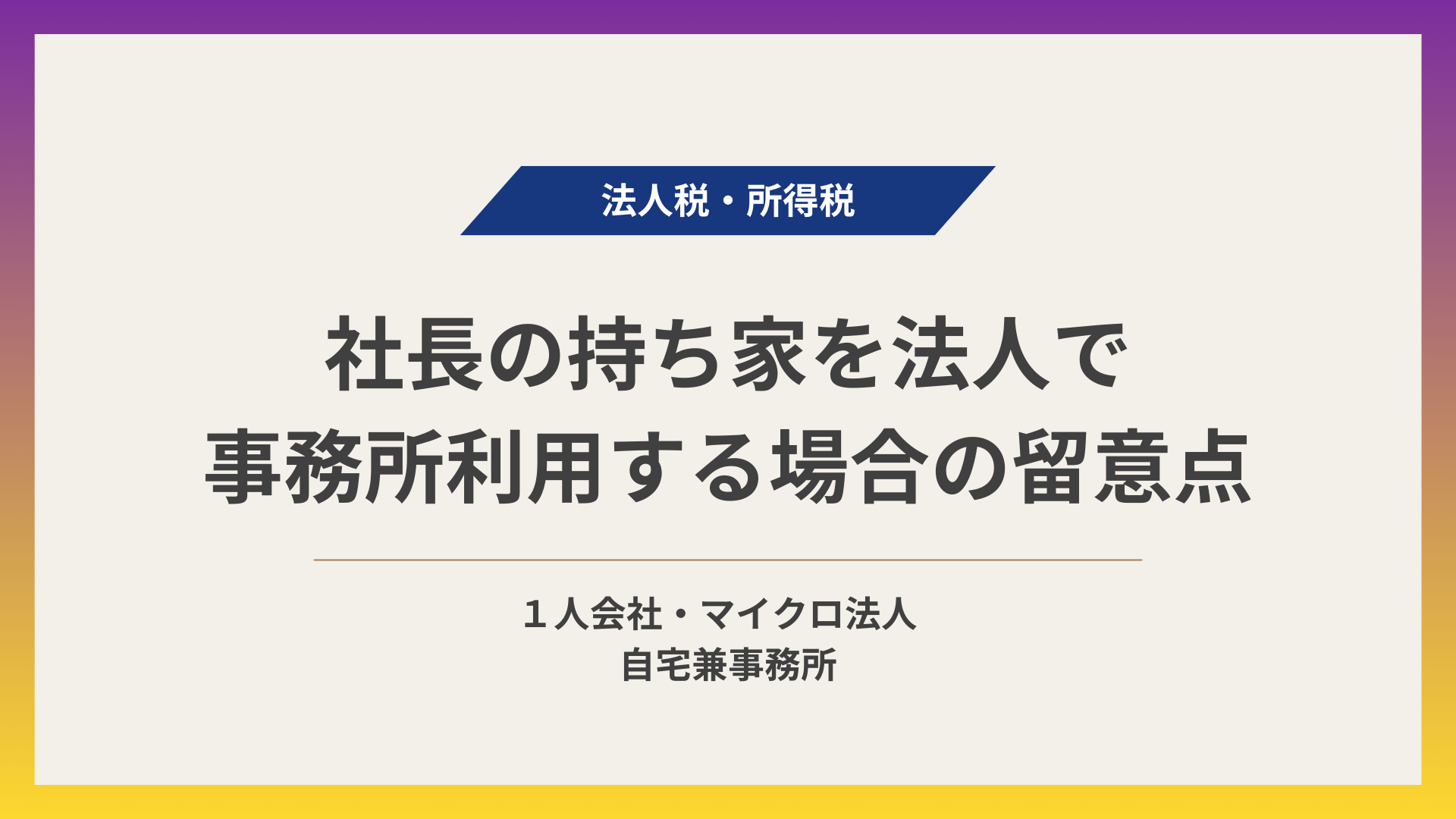
全体を通して重要なポイントは、下記2点
① 法人には「家事関連費」という規定がありません。そのため、家事按分割合(事業利用割合)を算出して按分するといった会計処理は基本的に出来ません。
② 社長個人と社長が株主である法人は法律上は別人格であり、他人同士として取引する必要があることです。株主(出資者)が社長1人の場合は、社長と法人の間で自由に融通(利用許可や価格調整)することが出来てしまいますが、法人というのは社長とは別人格なので第三者と同一の条件で取引を行う必要があります。
そこで、考えられうる自宅兼事務所(自宅兼本社・自宅兼事業所)の経費算入方法と留意点を以下で3つ挙げてみます。
1.社長が借りている賃貸物件を法人に賃貸する方法
社長が既に借りて居住している賃貸物件の一部を法人で利用したい場合には、社長個人と法人との間で建物賃貸借契約書(転貸借契約)を結んで転貸することになります。
この時の賃料は社長と法人はあくまで他人同士と捉えた時価(第三者価格)で値決めする必要があります。
そうはいっても類似の転貸相場としての事例は殆ど存在しない、あったとしても知る術がないと想定されますので、実務的には転貸面積など客観性のある基準で賃料総額を按分した上で一定率の利益を付加する等の方法で転貸賃料を決定せざるを得ないと考えられます。
なお、留意点として、社長側の処理として、法人から受け取ることになる家賃を社長個人の不動産所得として収入として算入する必要があります。ただし、同額だけオーナーへの家賃の支払いがあるので通常は所得は少額あるいはゼロになります。
このほか、借りているものを法人に貸すということはつまり転貸するということになるので、社長は法人に使用させる前に、オーナーの承諾を得ておく必要があります(民法612条)。また、用途を居住用として賃貸借契約しているものに法人の登記を行った場合には契約違反になる可能性があるので注意が必要です。
上記をふまえると社長が借りている賃貸物件の一部を法人で利用して法人の費用とすることは若干ハードルが高いように思われます。自宅を法人の活動拠点にする場合には個人事業のままで続けるというのも現実的と考えらます。
2.法人で賃貸物件を借りて社長に転貸する方法
社長が既に住んでいる賃貸の自宅があって、そこを法人で利用したいという流れの方が圧倒的に多いと思いますが、法人名義で賃貸物件を借りて、その物件の一部を社長の自宅として利用する方法も考えられます。
この場合は上記1.とは反対に、法人から社長に転貸することになります。同様に転貸価格は第三者価格により設定した上で、転貸借契約書を締結しておくことが望ましいと考えられます。
なお、留意点としては、そもそも事務所・居住用で兼用可能な物件は選択肢が限られる点や、小規模な法人が法人契約する際にオーナー審査を通過するのに難易度が高いという点が挙げられます。
3.法人が賃貸物件を借りて役員社宅として利用する方法(借上社宅)
この方法は役員社宅として法人の名義で賃借することで、経費に算入する方法です。
この場合は、役員の社宅として居住部分と事務所利用部分を含めて賃借料の100%が法人の費用(経費)に算入されます。ただし、「賃貸料相当額」を役員自身が法人に支払わなければなりません(法人では雑収入で計上)。
賃貸料相当額は以下のように算出します。マンションの場合は床面積が100㎡以上となることは稀ですので多くのケースでは小規模社宅に該当します。
| 区分 | 賃貸料相当額の算式 |
|---|---|
| 小規模社宅の場合 ※法定耐用年数が30年以下の建物:床面積132㎡以下 法定耐用年数が30年超の建物:床面積が99㎡以下 | 下記①~③の合計額 ① その年度の建物の課税標準額 × 0.2% ② 12円 ×(建物の総床面積㎡÷ 3.3㎡) ③ その年度の土地の課税標準額 × 0.22% |
| 小規模でない社宅の場合 ※法定耐用年数が30年以下の建物:床面積132㎡超 法定耐用年数が30年超の建物:床面積が99㎡超 | 下記①、②のいずれか高い金額 ① 上記小規模社宅の賃貸料相当額 ② 法人が地主に払う家賃×50% |
賃貸料相当額は法人が実際に負担している家賃よりも相当低く算出されることが多いため、結果的に法人で多くの経費が計上されることになります。なお、上記の課税標準額というのは、オーナーであれば容易に把握できますが、賃借人であっても賃貸借契約書があればその物件が所在する市町村役場で閲覧請求を行うことが出来ます。これらの情報収集の煩雑さもあり、実務上は小規模でない社宅と同様に50%を賃貸料相当額として多めに徴収している事例もあるようです。
4.まとめ(特に注意すべき点)
自宅兼事務所の処理の適切性が問題になるケースの多くはのちのち税務調査が入った時です。ここまでの留意点をチェックリスト化して以下にまとめます。
- 転貸借契約書が作成されているか?
- 転貸料金の算定基準(単価・数量の基準)は適正か?客観性はあるか?
- 面積基準で転貸している場合、時間帯によって転貸対象の区画をプライベートで利用してしまっていないか?
- 面積基準で転貸している場合、その区画を転貸したら明らかに生活が出来ないと言える状況になってしまっていないか?
- 社宅扱いする場合には適切な賃貸借相当額を収受しているか?
- 転貸、利用用途についてオーナーの承諾は得られているか?