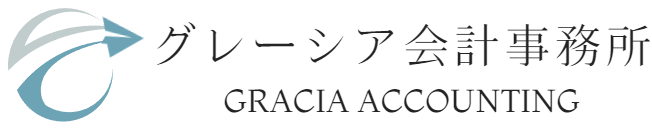葬祭費・埋葬料(埋葬費)の請求手続と税金の取扱い

葬祭費・埋葬料(埋葬費)とは
葬祭費・埋葬料とは、葬儀や埋葬を行う人に一定金額の支給を受けることができる給付金制度です。
葬祭費、埋葬料はどちらか一方のみ受け取ることができ、亡くなった方が加入していた健康保険制度によってどちらを請求できるかが異なります。
給付を受けることができる金額は概ね5万円程度になります。
たとえば投稿日現在、葬祭費の場合は大阪市、神戸市、京都市、吹田市、豊中市、高槻市は5万円の支給を受けることができます。
葬祭費・埋葬料(埋葬費)の請求方法
葬祭費・埋葬料の請求については、以下の要領で行うことが出来ます。ご相続があった場合、期限までに忘れずに申請しておきましょう。
| 自営業者の国民健康保険 後期高齢者医療制度 | 会社員の健康保険 | |
|---|---|---|
| 請求できるもの | 葬祭費 | 埋葬料(埋葬費) *1 |
| 金額 | 3万円~5万円程度 | 5万円 |
| 請求先 | 亡くなった方が住んでいた市区町村役場 | 亡くなった方が加入していた健康保険組合、協会けんぽ |
| 請求できる方 | 葬儀を行った喪主 | 亡くなった方に生計を維持されていて、埋葬を行った方 *2 |
| 期限 | 葬儀日の翌日から2年以内 | 死亡日の翌日から2年以内 (埋葬日の翌日から2年以内) |
*1:埋葬費は埋葬料を受け取る遺族がいない場合に支給される給付金で、生計を維持する関係にない方が埋葬を行った場合に支給されるものです。
*2:生計維持の事実関係は、同居の場合は住民票等により確認されます。別居の場合は預貯金通帳や、公共料金の領収書の写し等により生活費の負担関係などが確認されます。なお、生計を維持される関係であればよく、亡くなった方との血縁関係は問わないとされています。
提出が必要な書類・資料は申請書のほか、葬儀代の領収書等があります。自治体によって異なっており具体的な請求方法は各自治体のホームページで確認できます。請求後、おおむね1ヶ月以内くらいで振り込まれるようです。
葬祭費・埋葬料の税金の取扱い
税金の課税関係は以下の通りになります。
相続税の取扱い
➔ 葬祭費・埋葬料の受給権(収入)に対して相続税は課税されません。
葬儀会社に支払う葬式費用が相続財産からマイナス(控除)することが出来るならば、その補填とも解釈できる葬祭費・埋葬料の受給権は逆に相続財産として課税価格にプラスしないといけないかと思うかもしれません。しかし、葬祭費の受給権は、喪主にあります。喪主の権利であり被相続人の権利ではないため、相続税の課税財産ではありません。
所得税の取扱い
➔ 葬祭費・埋葬料の収入に対して所得税は課税されません。
たとえば後期高齢者医療制度の場合、高齢者の医療の確保に関する法律第63条で「租税その他の公課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と規定されています。このため、喪主の所得税は非課税になります。他の健康保険制度も同様に非課税の旨が規定されています。
[PR] 関西圏の相続税、贈与税申告はグレーシア会計事務所にお任せください。
当事務所は大阪市淀川区の相続に強い税理士事務所(会計事務所)です。
「相続が起きたけれど相続税がかかるかどうか分からない...」
「相続が起きて何から手をつけて良いか分からない...」
「会社員をしていて資料収集や税務申告まで十分な時間が取れそうにない...」
「自分でやってみようと思ったけど合っているか分からないし税務調査が不安...」
相続にまつわる専門的なお悩みに対して、相続のプロフェッショナルがスムーズな財産承継を目指し、適切な申告と納税完了まで丁寧にサポートさせていただきます。
最近ご相続が発生されて相続税申告でお困りの方や、生前贈与についてでお悩みの方はぜひお問い合わせ下さい。
公式LINEまたはWeb予約フォームより24時間お問い合わせを受付しています。また、初回ご面談は無料です。
サービス内容の詳細は、相続税申告の案内ページ、贈与税申告の案内ページからご覧いただけます。