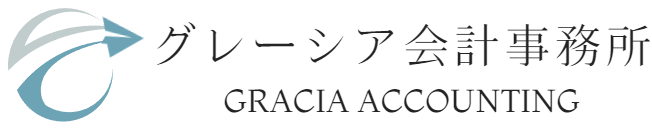【新リース基準】フリーレントの税務処理が明確化【R7年改正通達】
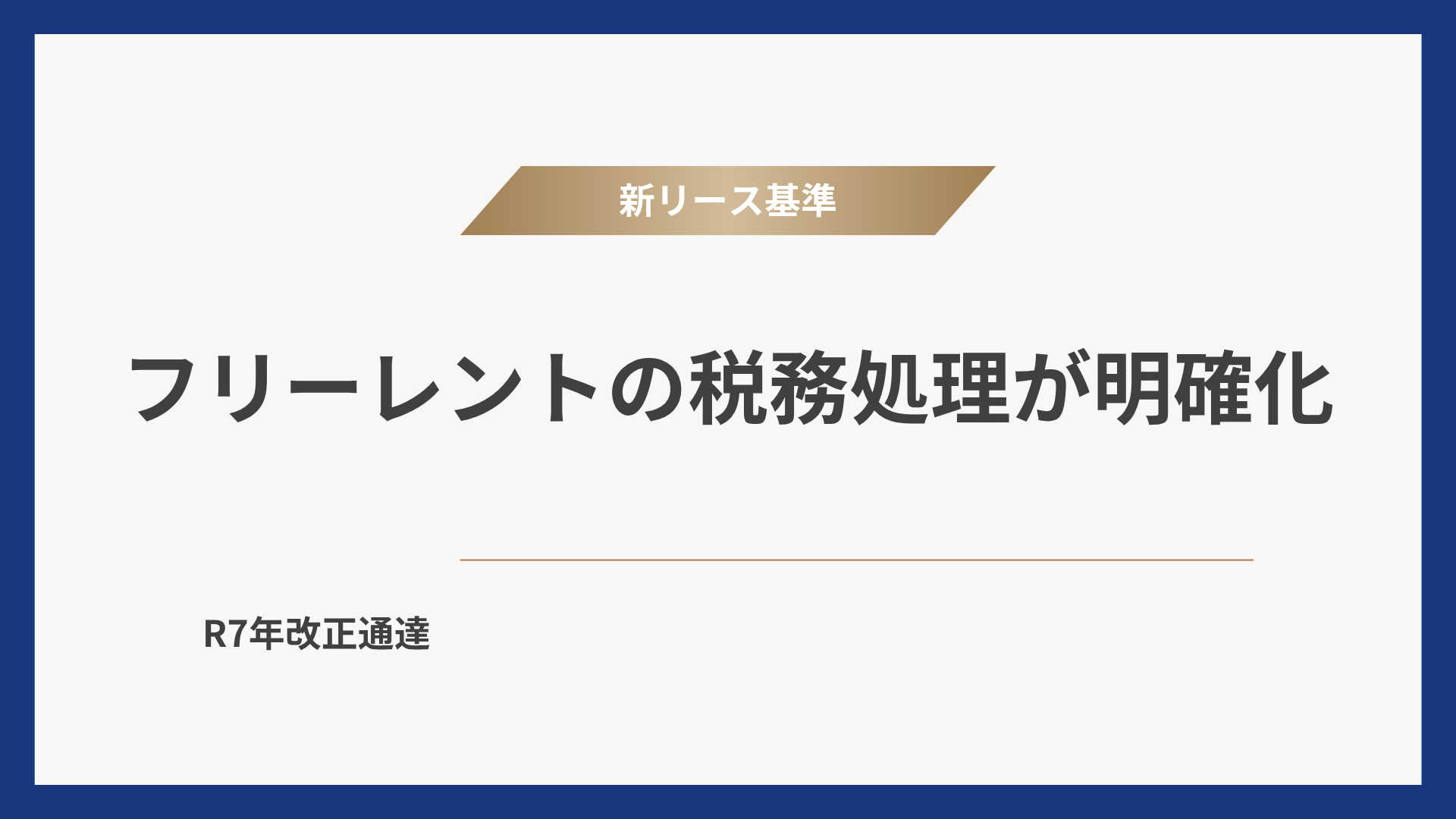
※【免責事項】当記事は投稿日時点に施行される法令に基づき一般的な取扱いを記載したものです。閲覧者が当記事を参考にして行った税務申告は閲覧者自身の責任によって行われ、当記事の内容に誤りがあり閲覧者に損害が生じた場合でも当事務所は責任を負いません。
事業者が店舗やオフィス(事務所)を借りる際、契約開始月から3カ月は家賃が無料など、賃貸物件の契約において入居後一定期間の家賃が無料になる契約を行うことがあり、これをフリーレント契約(Free Rent)と呼びます。
フリーレント期間の会計処理の考え方について、実務的には2つの方法があります。
1つは、支払いが発生しないフリーレント期間中には会計処理をせず、フリーレント期間終了後、実際に賃料が発生した時点で、支払額を費用計上する方法(A法)です。現金主義的な思考の会計処理になります。
もう1つは、契約期間の賃料総額をフリーレント期間を含めた契約期間で按分して実質的な1月当たりの負担額を算出し、その額を賃借開始時から費用計上する方法(B法)です。こちらは、フリーレントは賃料後払いと捉えた発生主義的な思考の会計処理になります。
A法は実際に支払った額を費用計上するだけでという単純な会計処理のため、中小企業の実務でよく採用されていると思われます。ただし、会計処理は簡便ですが、損金化される時期が遅くなるので税金的には不利な方法ではあります。一方で、B法では、フリーレントは価格と支払時期の調整に過ぎず経済実態としてはフリーレント期間を通じて均等に費用が発生していると考えられることから、上場企業など企業会計基準が適用される会社ではB法の方が望ましい処理であると考えられます。損金化される時期が早まるので税金面でも有利です。
これまで税法ではフリーレントについてどのように取扱うべきかかが明文化されていませんでした。今回、新リース基準の制定を背景として国税庁の通達が改正されており、フリーレント時の税務上の処理が明確化されています。
結論としては、一部の例外的な契約を除いて、A法、B法どちらの方法も採用できると考えられます。
フリーレント期間中は会計処理しない方法(A法)は改正後も採用可能
通達を参照する前にまず法人税法の本法を確認します。
法人税法 第53条
内国法人が資産の賃貸借で第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引以外のもの(以下この項において「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行つた場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額(その資産の賃借のために要する費用の額又はその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、次に掲げる額に該当するものを除く。)があるときは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 第22条第3項第1号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額
二 固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
上記は売買に該当しない賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)の場合の規定です。フリーレント条項が盛り込まれるような不動産の賃貸借契約は上記の賃貸借取引該当することが多いと想定されます。
次に、「債務の確定した部分の金額は、」と規定されています。フリーレント期間については、賃貸借期間は経過しているものの、賃貸借契約上の賃料支払義務が成立しておらず、債務が成立していないことから、フリーレント期間に対応する賃料相当額は損金算入出来ないものと考えられます(平成30年6月15日裁決事例・財務省 令和7年 税制改正の解説 参考)。
そのため、法人税法で規定されている計算方法としては、「賃料の支払時に費用処理する方法(A法)」となります。
新設された法人税基本通達12 の 5- 3- 2のポイント
賃料総額を按分する方法(B法)による会計処理が出来ることが明文化
今回新設された通達の内容を確認します。
(無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入)
12 の 5- 3- 2 賃借期間のうち賃料の支払がない又は通常に比して少額である期間(無償等賃借期間)が定められた契約のうち、次に掲げる場合に該当するなどの課税上弊害があるもの以外のものに基づく法第 53 条第1項に規定する賃貸借取引に係る当該契約に基づき支払うこととされている金額についての同項の規定の適用に当たって、当該金額が当該賃借期間にわたり支払われるべきものとした場合に各事業年度中に支払われるべきこととなる金額(当該事業年度終了の日までに損金経理をした金額に限る。)を当該各事業年度の損金の額に算入するものとする。
国税庁 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)より
少し読みづらいですが、ポイントは以下です。
・フリーレント契約については、契約期間の賃料総額をフリーレント期間を含めた契約期間で按分して実質的な1月当たりの負担額を算出しその額を賃借開始時から費用計上を行う方法で計算する(前段落のB法)。
・上記処理を行うためには損金経理することが要件とされ、申告調整による損金算入は出来ない。損金経理を行えば上場企業だけでなく中小企業もこの方法で計算することが出来る。
・課税上弊害があるものはこのB法で計算することが出来ない(後述)。
按分計算する場合の「課税上弊害があるもの」とは?
通達の続きです。「次に掲げる場合に該当するなどの課税上弊害があるもの」として例示が2つ挙げられています。
(無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入)
12 の 5- 3- 2 (続き)
⑴ 当該無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額と当該契約に基づき支払うこととされている金額との差額が当該契約に基づき支払うこととされている金額のおおむね2割を超える場合
⑵ 当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4月を超える場合に限る。)
国税庁 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)より
(1)は、フリーレントに相当する金額が契約に占める割合が大きすぎる場合です。
(2)は、1事業年度のうちフリーレント期間が長すぎる場合です。
按分計算する場合には、しない場合と比較して、損金計上時期が早くなるため、上記のようにフリーレント期間の影響が大きくなるような契約については損金算入時期をB法で処理することが制限されているものと考えられます。
まとめ
・フリーレント期間は会計処理しない方法(A法)、賃料総額を契約期間で按分してフリーレント期間も費用計上する方法(B法)どちらも採用できる。
・B法は損金経理することが要件。また、課税上弊害があるような賃貸借契約の場合は適用出来ない。
適用開始時期はR7年4月1以後開始する事業年度分となります。